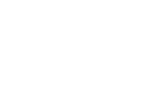2025年04月01日
パーソナルジムNEXUS白金台店 有酸素運動とダイエット・筋肥大の関係性について
ブログ
目次
有酸素運動(ランニング、サイクリング、水泳など)は、ダイエット(減量)と筋肥大(筋肉の成長)に異なる影響を及ぼします。それぞれの関係性を詳しく解説します。
1. 有酸素運動とダイエットの関係
① カロリー消費と脂肪燃焼
有酸素運動は、酸素を利用してエネルギーを生み出す運動で、主に脂肪と糖質を燃料とします。ダイエットでは「消費カロリー > 摂取カロリー」の状態が必要であり、有酸素運動は消費カロリーを増やすために効果的です。
また、低~中強度の有酸素運動(最大心拍数の50~70%程度)は脂肪を優先的に燃焼しやすいとされています。
② 基礎代謝の向上
有酸素運動を継続すると、心肺機能が向上し、筋肉内のミトコンドリア(エネルギーを生み出す細胞器官)の活動が活発になります。その結果、基礎代謝(何もしなくても消費するエネルギー)が向上し、脂肪が燃えやすい体質になります。
③ 筋肉量の減少リスク
過度な有酸素運動は、エネルギー不足を引き起こし、筋肉の分解(カタボリズム)が促進される可能性があります。特に長時間の有酸素運動(1時間以上)を頻繁に行うと、筋肉もエネルギーとして分解されることがあるため、筋肉量を維持したい場合は注意が必要です。
④ 筋トレとの組み合わせ
筋肉を維持しながらダイエットを成功させるには、有酸素運動と筋トレを組み合わせるのが理想的です。筋トレを先に行い、その後に有酸素運動を行うと、筋分解を抑えながら脂肪を効果的に燃焼できます。
2. 有酸素運動と筋肥大の関係
① 有酸素運動の影響
筋肥大(筋肉の成長)は、主に筋トレ(無酸素運動)と十分な栄養摂取によって起こります。有酸素運動は、筋肥大に対して以下のような影響を与える可能性があります。
ネガティブな影響
カロリー不足:有酸素運動によるカロリー消費が大きすぎると、筋肉を成長させるためのエネルギーが不足し、筋肥大が妨げられる。
筋分解(カタボリズム):長時間の有酸素運動は、筋肉のタンパク質を分解しやすくする。
筋トレ後の回復遅延:筋トレの後に強度の高い有酸素運動を行うと、回復が遅れ、筋肥大に必要な回復時間が確保できなくなる。
ポジティブな影響
血流促進と回復促進:軽めの有酸素運動(ウォーキングやジョギング)は血流を促進し、筋トレ後の回復を助ける。
持久力向上:筋肉の持久力が向上すると、高重量トレーニングでも長時間集中でき、結果として筋肥大の効率が上がる。
② 筋肥大を目指す人の有酸素運動の取り入れ方
筋肥大を優先する場合、有酸素運動の取り入れ方には注意が必要です。
有酸素運動の頻度:週2~3回程度に抑える。
強度:軽め(ウォーキング、ジョギング、バイクなど)。
時間:20~30分程度(長時間の有酸素運動は避ける)。
タイミング:筋トレと同じ日に行う場合は**筋トレ後に**(筋トレ前に有酸素運動をすると、筋トレのパフォーマンスが落ちる)。
まとめ
有酸素運動は脂肪燃焼に有効で、基礎代謝を向上させるが、やりすぎると筋肉の分解を招く可能性がある。
ダイエット目的なら、有酸素運動と筋トレを組み合わせるのがベスト。
筋肥大を優先するなら、有酸素運動は軽め・短時間に抑えるのが理想。
筋トレと有酸素運動のバランスをとることが、理想的な体づくりのカギになる。
自分の目標に合わせて、有酸素運動を適切に取り入れよう!
NEW ARTICLE
ARCHIVE
- 2026年2月
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年2月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年8月
- 2022年1月
- 2021年10月
- 2021年1月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年2月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年9月
- 2018年8月